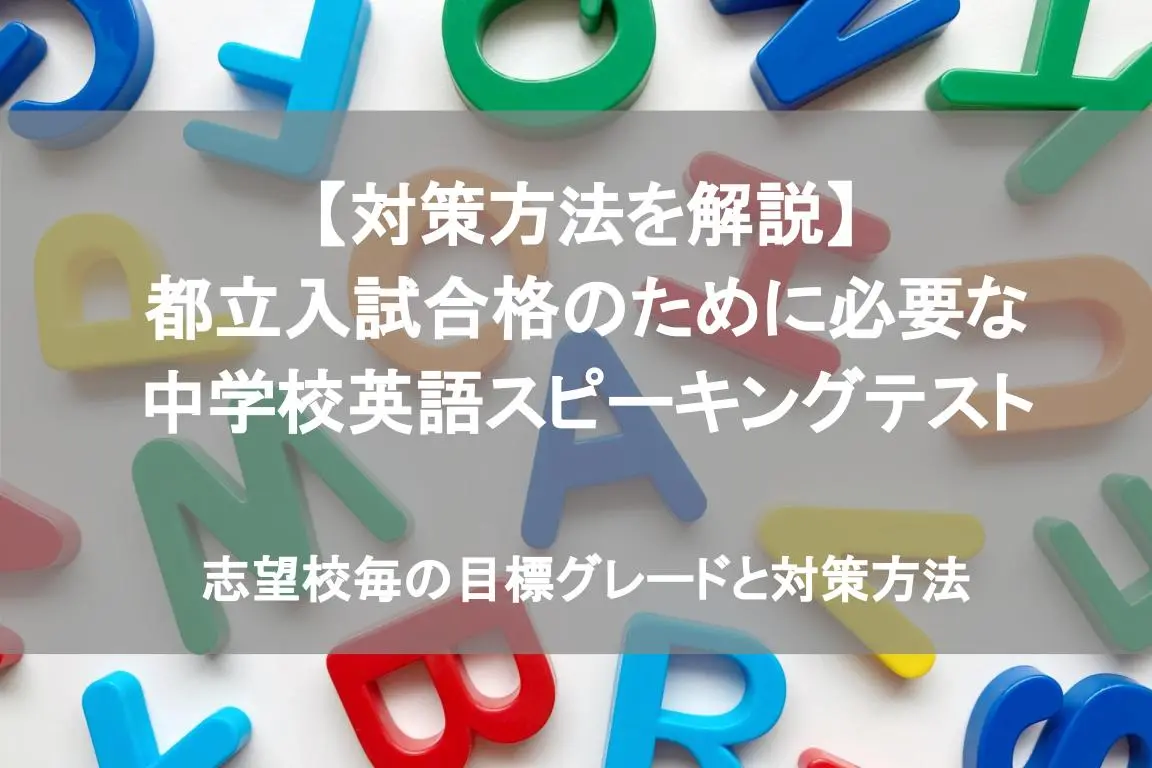
中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)についての概要はこちらの記事を参照ください。
今後の勉強方法を説明する前に、具体的にどのグレードを目指すと都立入試の合格につながるのかについて説明します。
目標とする都立高校毎のグレードの目安
町田や日野台・豊多摩・調布北ななど偏差値が60を超えるような地域の都立上位高校を目指す場合はグレードC(12/20点)、その他の都立高校を目指す場合はグレードD(8/20点)を目標としましょう。
前提として、ESAT-Jのスコアが1点とれればグレードEになります。そのため、最低限の準備をすれば全員がグレードEをとれるはずです。その上で、まずは1つ上のグレードDをとれるようにする。さらに上位校を目指す場合は、もう1つ上のグレードCをとれるようにするとを目標とします。
目標とするグレードの理由について
「もっと上のグレードを目指したい」と思った人もいるかもしれません。ただ、ESAT-Jの対策に時間をとりすぎるのは、都立入試合格という観点からみると効果的ではなく、「いかに短い時間でESAT-Jの最低限の対策をするか」が都立入試合格への近道になります。その理由を2つ説明します。
ESAT-Jの入試における影響が小さい
前回記事の「ESAT-Jの評価方法」にも書きましたが、ESAT-Jはグレードが1つ変わると、1020点換算で4点の影響がでます。
それに対して、5科目(英数国理社)の内申が1つ上下すると約4.6点の影響があり、実技科目(音美技保)の内申が1つ上下すると約9.2点の影響があります。
日程が内申点に影響する定期テストに近い
令和6年度のESAT-Jは11/24(日)に実施されましたが、入試にもっとも影響する内申点(仮内申)が発表される直前の最後の定期テストは、どの中学校も11月中旬〜11月下旬に集中していました。ESAT-Jと定期テストの日程がかぶることからも、両方の対策に時間を使うことは、現実的には難しいと言えます。
このような背景から、都立入試での合格を考えれば、定期テストに注力したり、提出物を整えて内申点(仮内申)を1つでも上げることに注力したりする方が効果的なので、先ほどのような高校毎の目標を設定しています。
目標のグレードをとる対策方法
英語のスピーキング力を短期間で上げることは難しいので、このESAT-Jの練習では「今のスピーキング力でESAT-Jのスコアを上げる」ことを目的とします。その上で大事なのが以下の3点です。
読めない単語があっても、発音するのをやめたり、先生に質問したりしないこと
ESAT-Jでは発音が間違っていても点数がもらえるので、分からない単語でも発音したほうがスコアにつながります。
たとえば、「月曜日」という意味の Monday という単語の読み方がわからなくても「モンダイ」や「モンデー」と発音できるようになることが重要です。単語がどうしても読めなかったら、ローマ字読みをするのがオススメです。
無理に文の意味を考えない過ぎないこと
ESAT-Jは「声を出す」テストです。とくにPartAは文の意味が分からなくても、読めば点数につながるので、無理に意味を考えるのではなく、ひたすら目の前の単語を読んでください。
マイクの録音が認識してくれるほどの大きい声をだすこと
声が小さすぎると、録音された音声が聞き取りづらく点数につながりません。できる範囲でいいので、普段から大きい声を発声して練習をします。
勉強方法
先ほどの「ESAT-Jで目標のグレードをとるのに大事なこと」を身につけて実践するために、声をだして読む練習(=音読)を積んでいきます。コノ塾では、200単語ほどの実際の入試での過去問の英文を用いて、英語の授業でESAT-Jの対策をしています。ここではコノ塾での取り組みをご紹介します。
「英文を読むスピード」の対策
ESAT-JのPartA問題では30秒間で約40単語を読み上げる必要があります。
実際に声をだしてみようとすると、英文を声にだすことに慣れておらず、
「つっかえながら読んでいて、時間内に読み終わらない」という問題が起こります。
コノ塾では、英語の授業の最初の時間で、1分間の制限時間内で英文を音読する練習をしてもらっています。
音読の際は「分からない単語はローマ字読みでもいいから発音して読み進めること」を徹底しています。
また、上手く読み進めることができていない生徒さんには講師が声をかけるようにしています。
これにより、生徒さんは音読に慣れ、1分間で読める英文の量が増えます。
8月からこの練習を開始しますが、たった1週間の練習するだけで、1分間で読める単語数が30以上増えている生徒さんも多くいます。まずは音読に慣れることが重要なのです。
「声が小さいこと」の対策
普段音読に慣れていなかったり、自信がなかったりすると、声が小さくなってしまうことがあります。
ESAT-J は、先生や面接官に向かって話すのではなく、タブレットに向かって発音をします。
人が相手であれば、もし聞こえなければ聞き返してくれることもありますが、タブレットは聞き返してくれないので、「声が小さい=発音が聞き取れない」として、採点の対象外になります。
そこでコノ塾では、自分が発音した音声をスマホに録音し、十分に聞き取れる音量なのかを確認しながら音読のトレーニングをします。また、先生が練習を聞いて、声が小さいと感じるとき、録音した音声をきかせてもらい、もっと大きい声で話すようにアドバイスしたりします。
こうすることで、「どれくらいの声を出せばいいのか」「今どれくらい大きな声で話せているのか」を把握できます。
とくに ESAT-J の練習を始めた最初の時期は、先生に手伝ってもらいながら、自分の音声について「自分の声はこんなに聞き取りにくいのか…」「もっと大きな声で発音しないと」といった気づきを得て、修正していく作業に取り組むことが大切です。
その他の情報
以前にも書いた通り、ESAT-Jよりも内申点・入試の方の配点が大きいので、
ESAT-Jはより少ない時間で効率的に練習をすることが重要です。
コノ塾では英語の授業の数分間を使って、効率的に対策をしています。
ESAT-J についてご不安な方は
コノ塾ではESAT-Jの対策はもちろん、都立受験に必要な5教科の内申・定期試験対策、進路指導を実施しております。
まずは話を聞きたい、相談したいという方も大歓迎です。
常時無料体験を実施しておりますので、お近くの教室までお問合せください!
監修者 中嶋広大
大手学習塾で、最難関校受験コースの教室長、本部映像授業責任者を歴任。英語の動画教材においては、中学全学年の制作を担うなど、塾業界での英語教育のエキスパート。また東京エリアの教務・進路責任者として、自校作成校を含む都立高校受験での進路指導や教材・カリキュラムの設計など、都立受験の経験も豊富。現在は、コノ塾で英語教材の制作・開発の責任者として、ESAT-J対策含む英語指導のカリキュラムを担当。